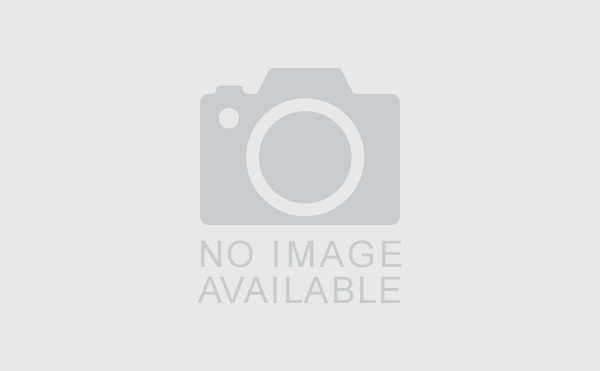FPコラム No43【東証上場企業を取り巻く情勢について(その2)】 2025.4.2
アベノミクス3本の矢の一つである成長戦略の中で、これまでの約10年間、日本の政官界においては、東証上場企業の株主重視の経営に転換させるための政策が継続してとられてきました。
その結果、上場企業は、自社株買いや政策保有株の解消、増配などの配当株主還元策に積極的に取り組むようになり、日経平均株価は昨年、ようやく平成バブルの最高値を、34年ぶりに更新する結果となりました。
しかしながら、その背景にあるのは、外国人投資家の潤沢な資金力を原資とした日本株買いであります。
東証のうち、7割の売買シェア、3割の株式保有率を外国人投資家が占めています。
この要因となったのが、東証株価の長期的な低迷と、日本企業の時価総額順位の世界的な低下であります。
平成バブル期においては、世界における時価総額トップ10のうち日本企業が上位7社を占めていましたが、今日においては50位以内にはトヨタ1社のみが、かろうじてランクインしている状況です。
この34年の長い月日の流れの中で、日本経済は著しく衰退をし、日本の国力低下と日本人の国際的な貧困化が進行してしまいました。
一方では、日経平均株価の上昇とともに、フジテレビの株主提案や、セブンアンドアイの買収をめぐる騒動など、外資勢アクティビスト(物言う株主)や外資ファンドによる上場企業への経営干渉や経営介入など、その影響力が過去に比べると劇的に増している状況にあります。
バブル期のような日本経済の絶対的な影響力が低下したことで、このように、日本企業が国際的なグローバルスタンダードに取り込まれ、あるいは金融資本主義の荒波に飲み込まれることは、受け入れざるを得ない事態であるといえるでしょう。
実は、今日の経済をめぐるこれらの状況の基盤となったのが、2004年の会社法施行でした。
当時は、派遣法改正、郵政や各行政の民営化、DC(確定拠出年金)制度の導入、ロースクールの設置や弁護士人口の増加の司法制度改革など、本格的な日本改造計画が実行された時期でもありました。
それらの構造改革を基に、20年の時を経て今日の日本経済の取り巻く厳しい環境があります。
しかしながら、その状況の中において、今後の日本が存続し発展していくためには、我々は、「日本人特有の真面目さ、誠実性、緻密さ、などの精神性」を固有の基盤とした技術や製品、新たな価値を創造し、世界に発信提供していかなければならないものと考えます。